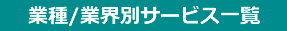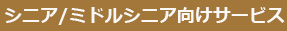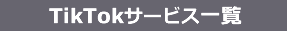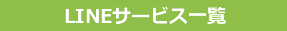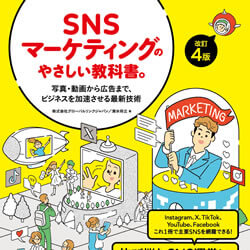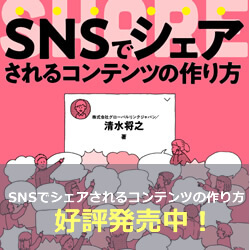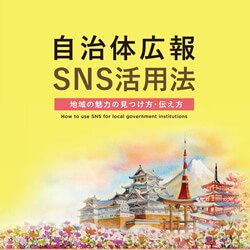独自性がなく繰り返しの多いコンテンツはYouTubeからの評価が下がる
近年はAIツールの普及により、動画生成が容易になっています。カメラや機材を用意することなく、プロンプトを入力するだけで動画が制作できるようになりました。特に短尺動画であるYouTubeショートの場合、大量に生産しておけば自動再生によって視聴数を稼げるケースがあり、簡単に収益化する手段として利用している投稿者も存在しています。
こうした状況を受け、2025年7月にYouTubeはパートナープログラムのポリシーを厳格化し、独自性がなく繰り返しの多いコンテンツの収益化を制限することを発表しました。Search Engine Landが、YouTubeで急増する複製コンテンツの影響と対策について解説しています。
付加価値があれば既存コンテンツの再利用は認められる
YouTubeが独自性がないと判断するコンテンツの例としては、他の記事やニュースをAIで読み上げるだけの動画、音程や再生速度を変えただけの楽曲、音声解説のないスライドショーなどが挙げられています。ほとんど違いのない重複した動画や、同じフォーマットを大量に複製したものも対象に含まれます。
一方で、独自の要素を追加した上で既存のコンテンツを再利用することは許容されています。例えば、同じ学習教材であっても、わかりやすく解説を加えたものであれば問題ありません。同様に、ス
ポーツや映画の批評、ユーモアを交えたリミックス動画、独自の音声吹き替えといったコンテンツは規制の対象外です。
マーケティング担当者は多様でユニークな動画制作を目指す必要がある
企業のマーケティング担当者は、YouTubeのポリシーを理解し、スパムと判定されるような大量生産コンテンツを投稿するのは避けるべきです。AIは動画制作者を置き換えるものではなく、それを補助するツールであると捉え、各コンテンツが独自の価値を持つように構成する必要があります。短いコンテンツであっても付加価値を与え、多様なフォーマットでコンテンツを制作することが重要です。
まとめ
AIで動画制作が容易になったからといって、単純な再生数だけを指標にすると、ユーザーにとって価値のあるコンテンツを提供できず、プラットフォームからの評価も下がってしまいます。ユーザーにとって有益なコンテンツを作成し、視聴時間を延ばせるよう、独自のコンテンツ戦略を立案するようにしましょう。
The Fujiwhara effect on YouTube: AI, Shorts, and the rise of duplicate content
Author:Takayuki Sato