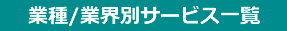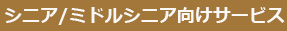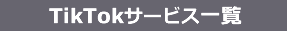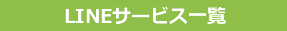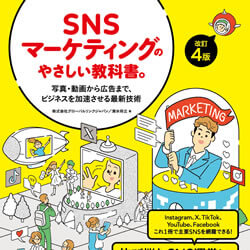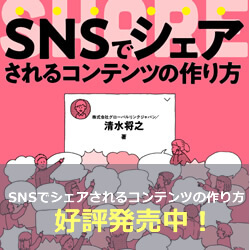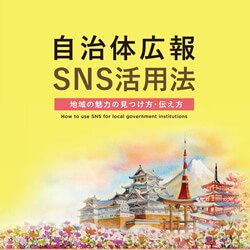YouTubeは2025年、「Made on YouTube 2025」において生成AIを活用した新ツール群を発表しました。これにより、従来は多くの工数を要した動画制作が効率化され、企業がマーケティングや情報発信で動画を活用するハードルが下がる可能性があります。一方で、AI生成コンテンツならではのリスクも存在するため、日本企業が活用する際には戦略と同時にルール設計が欠かせません。
Z世代が示す動画消費の変化
背景には、情報収集のスタイルそのものの変化があります。特にZ世代は「検索エンジン」よりも「SNS動画」を情報源として重視する傾向があると各種調査で指摘されています。商品や企業理解の第一歩としてYouTube Shortsを視聴するケースが増えており、こうした流れを受け、YouTubeは短尺動画に特化したAIクリエイション機能を拡充しています。
YouTube公式が発表した新機能と動向
Veo 3 Fast
Google DeepMindの動画生成AI「Veo 3」をベースにした新機能。プロンプト入力から短尺動画を生成でき、YouTube Shortsに統合が予定されています。音声付与機能についても一部発表や報道で紹介されています。
Edit with AI
スマホ内の素材をAIが解析し、“初稿(first draft)”を自動生成する編集支援機能。音楽やトランジションの追加なども紹介されていますが、あくまで支援機能であり、最終的な編集は人間が担う前提です。
Shortsの指標変更
2025年3月末より、Shortsのビューは「再生開始」ベースに変更されます。従来の「視聴時間に基づく評価」はEngaged viewsとして残り、収益化も引き続きこれを基準とすることが案内されています。
Shopify連携
米国でShopify Plus/Advancedの事業者がYouTubeショッピングと直接連携可能に。動画から商品ページへの即時誘導が容易になりました。
実践に活かせるアクションプラン
AI下書き × 人の最終編集
生成AIで“初稿”を量産し、人間がブランドトーンや正確性を担保するフローを標準化することが重要です。これによりスピードと品質の両立が可能になります。
KPIの再設計
再生数は「到達」を示す指標に過ぎません。今後はEngaged views(質)やCTR(クリック率)、さらに購買や応募といった成果指標を組み合わせ、段階的に評価することが求められます。
静止画資産の動画化
YouTube公式が紹介する「Photo to Video」機能を活用すれば、既存の製品写真やイベント写真からショート動画を簡単に作成できます。リソースが限られる中小企業でも実行しやすい施策です。
動画とECの統合準備
米国で始まったShopify連携を見据え、商品タグ設計や在庫連動、ランディングページの整備を先行して準備しておくことで、日本展開が始まった際にスムーズに対応できます。
リスク管理の徹底
AI生成コンテンツは便利な反面、著作権・情報の正確性・プラットフォーム規約違反(BANリスク)への対応が必須です。社内で「生成素材の利用範囲」「編集・検証の必須プロセス」「クレジット表記ルール」などを明文化しておくことが望まれます。
まとめ
YouTubeの新しい生成AIツール群は、単なる制作効率化ではなく、マーケティング戦略そのものを進化させる可能性を秘めています。日本企業にとっての鍵は「量産×最適化×リスク管理」をいかに仕組み化できるか。今のうちに体制とルールを整えることで、先行優位を築くチャンスが広がります。
出典
YouTube公式ブログ:Unpacking the magic of our new creative tools (Made on YouTube 2025)
YouTube公式ヘルプ:A change to how we count views on Shorts